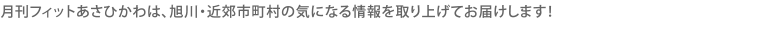admin
一次選考通過 『母の手』松井 遙
「生きている意味がわからない。私なんて、いなくなればいい」と口に出してみた。
傍らでその言葉を黙って聞いていた母。
何もかもがどうでもいいと、むしゃくしゃしていたあの日。
私は居た堪れなくなり、薄着のまま、吹雪の外へ飛び出した。
何も考えず、走り出したくなった。
視界は真っ白だ。
私はあろうことか、足を滑らせ川に転落した。
手足の痺れで気がついた、真冬の川の水の冷たさを知る。
私は自分の背丈よりも髙い、雪の崖から転落したのだった。
どんなに跳ねても、届きやしない。
雪の崖に手足を食い込ませようとしても、がりがりと崩れていくだけだった。
川に突っ込んでいる足がさっきまであんなに冷たかったのに、燃えているかのように熱く感じる。
「死にたくない」と泣きながら雪の崖を、感覚のない両手でよじ登ろうとしたってもう遅い。
このままだったら、生きていられないという事はわかった。
こんな吹雪の中、凍てつく川原を散歩している人がいる筈もないのだし。
「助けて!」という言葉だって、吹雪の声に掻き消される。
「私、さっきあんな事を口にしたから、罰が当たったのです」と、ただ思った。
軽率だった。
そんな中、私を呼ぶ母の声がした。
母は、一目散に川へ飛び込んできた。
何の迷いもない姿が、信じられない程だった。
寒さに震えながらも、雪の崖の上へ私を押し上げる母の手。
母のおかげで、私は助かった。
私は雪の崖の上から、凍えた手を母に差し出す。
しっかりと握られた母の手を精一杯、引き上げる。
心配かけて、ごめんなさい。
寒い思いをさせて、ごめんなさい。
馬鹿な娘で、ごめんなさい。
「帰ろう」と私の手を引く、母の手。
そうだった。
幼い日の帰り道も、そうだった。
ここにあるのは、いつだって変わらない、母の手だ。
「生きている意味がわからない。私なんていなくなればいい」なんて二度と口に出さない。
私は私に約束する。
あの時の母の手が、今でも私を支えている。
一次選考通過 『ああ、よかった』 P.N./大田さと
「母さん、今日はあったかいから散歩に出てもいいって先生が言ってたんだ。今車いすを用意してもらうから、少し待ってて」
お父さんの声が少しだけはずんでいる。今日から六月だって朝来た看護婦さんが教えてくれたのよ。天気もいいから、ご主人がいらしたら散歩に出られるかもしれませんねって。
だから今日はお父さんを心待ちにしてたの。嬉しいわ。私がそう答えると、私の体がゆっくりと浮き、そっと下ろされて温かな毛布が掛けられた。
久しぶりの太陽の匂い。子供の声。顔に柔らかくふれる風も、陽の温かさも、全部わかりますよ。何も見えなくても、何も話せなくても。
「朝病院に来る途中にライラックが咲いているのを見つけたんだ。白いやつでさ、きれいだったわ」
お父さんは笑みを含んだ声で私に話しかける。そして不意に車いすが止まった。
「ああ母さん。ほら、そこにも咲いてるわ。紫のライラックが」
そうね。いい香りがするもの。私は昔見たライラックの紫を思い浮かべると、ふと額にお父さんの分厚い手が触れた。
「アスパラの天ぷら、食いてえなあ。母さんの揚げるのが一番うまいもな。あと時鮭のフレークも。買ってきたフレークはなんだかうまくねえんだ」
お父さん、ごめんなさいね。倒れた日、買ってあった時鮭をフレークにしようと思ってたのよ。でもなんだか体がだるくて、明日でいいかって思ってしまったの。こんなことになるなら無理してでも作っておけばよかった。あんなの簡単にできるのに。引き出しのノートを見つけてくれるといいんだけど。そうだ、きっといつか里良が見つけてくれるわね。あの子が来た時はいつも私の引き出しを開けて色鉛筆を出してお絵描きしていたから。私は札幌に住む孫娘の里良を思い浮かべた。リラはライラックのフランス名だ。娘が新婚旅行で行ったフランスを気に入り、ライラックの咲く季節に生まれた娘に里良とつけたのだ。そうだ。あと三日で里良は四歳になる。私が病院にお世話になって二年になるんだから。
「明日里良の幼稚園の運動会だから、ちょっと札幌に行ってくるわ。正月以来会ってないもな。おっきくなってるべな」
お父さんはそういうと、またゆっくりと車いすを押してくれた。
月曜日。
「里良おっきくなってたわ。楽しそうだったあ。かけっこなんて隣の子とニコニコしながら走ってるんだ。そして二人して仲良くビリッケツでさ。大笑いさ」
お父さんは私の手を握り、本当に楽しそうに話を続けた。
「香里の作った弁当もうまかったわ。おにぎりの鮭フレークが母さんのと同じ味だったのさ。里良の好物が鮭フレークなんだって香里が笑うんだ。正月に里良が見つけた母さんのノート見て作ったらえらく気に入って、毎日ごはんにかけて食べるってきかないんだとさ」
ああよかった。心残りだったフレークをみんなに食べさせてあげられて。私安心したわ。みんなが幸せそうで。ありがとう。愛してますよ、お父さん。
一次選考通過 『お風呂やさんと私』 畑山 有希
「え~、うそぉ。今3月なのに…」北の春はいつも遅い。にしても、今年の雪融けの遅さは例年以上で、3月下旬だというのに、今もカーテンを開けた瞬間目に飛び込んでくる、うっすらと白い景色に思わず、声を上げる。早朝音もなく静かに積もったのだろう。
ここ、ナナカマドが、シンボルの花の、雪深い街で家を建てたのは、私が小学校高学年の時。
家のすぐ目先、歩いて2分の場所に小さな銭湯があった。すぐには利用せず、お湯が出なくなった…とか、夏あまりに、暑いので家でお湯を沸かさずに…とか何かきっかけがあり、利用し始めるようになったはずだ。
温泉は旅行等で行ったことがあったが、銭湯というのは記憶の限り初めてで、その脱衣所の狭さや、番頭さんが見える位置に座っていることに驚いた。しかし、すぐに慣れ頻繁に通うようになった。床の青っぽい畳、古い木造のロッカー、懐かしい響きの演歌。何故こんなにも心地よいのだろう。何故こんなにも、心静かに落ち着いていくのだろう。―ああ。似ているのだ。ここは、母が子ども時代を過ごした、祖母と曾祖母が2人で暮らしていた木造の古い家に―
こっくり、こっくり。
私は夜入りに行くことが多く、番頭の初老のおじさんは、いつも居眠りをしていた。どちらかというと、私は人見知りで、人の目を見て話すのが苦手だったので、逆にそれがありがたかった。
「お願いします」そっとお金を置く。「あっ!はいはい…。ちょうどね!」引き戸を開けて入ってくることに気づかなかったおじさんは、そこでやっと気付き、慌てて対応してくれる。
そんな冬のある日、珍しく閉店30分前のやや遅い時間に弟と出掛け、時間を肌理、待ち合わせをした。
時間になり、多分出ただろうと、靴をつっかけ、「どうも~」と出ようとした瞬間、珍しくおじさんが目を開き、「あっ。ちょっと待ってね」と私を静止した。「?」数秒して、「はい、いいよ~」との声の後、弟の「どうも~」といいガラガラ引き戸を開け外に出る音が聞こえてくる。「あ。はい。どうも」と外に出て、弟と並んで帰りながら、おじさんが私が思っているよりずっと見ていてくれてることを知る。姉弟って知っていたんだ。暗いし、家がこんな近いのも知らないもんな~。優しさにポッと心が灯る。
3月も今日で最後なのに、まだ一面雪景色。私は4月から本州の大学に進学する。受験勉強で忙しくなかなか来られなかった銭湯に久々に足を運ぶ。こっくり。こっくり。ストーブに照らされたいつもな赤い顔。言葉はなくても安心する空間。ざぶん。お気に入りのぬるめの湯に入る。「いいち。にいい」誰もいないので声に出してみる。何故か昔父と風呂でかけ算を練習したことを思い出す。帰りがけ、どうもといいかけ、いい直す「あの」「はい」おじさんがちょっと驚き、目を開く。私は、ゆっくりと不思議な程落ち着いた響きの声で、この地を離れることを伝えた。
言いながらだんだん我に帰り、さぁっと冷めゆく自分に気づく。私は何をくちばしっている!まともに口をきいたこともないのに……でも…「そうでしたか」おじさんは、いつもの表情からは想像もできないくらい、紳士のような真面目な面持ちで私を見た。そして、目を見て顔を上げ、一言「頑張ってね」そう言った。どこまでも、ただひたすらに優しい笑みを浮かべ。
外に出る。ひゅうと地吹雪く風。でももう春の風だ。「あ」泥混じりの雪の中に小さな花を見つける。いつから眠っていたのだろうか。小走りに歩きだす。ポカポカとする胸の温かさを感じながら。
~おじさん、元気でいてね~
一次選考通過 『さあ行くよ!』 利根川 嘉子
「さあ行くよ!」
息子を連れてこのプラタナスの坂道を何度登っただろう。
「連れて帰れない、どうしていいかわからないって言うんだよ」
そうドクターから連絡があるたび車を走らせプラタナスの坂道を登って行った。
息子はダウン症。今は何の抵抗もなく言えることが、13年前は誰にも言えなかった。
どうしていいかわからなくて、なぜ自分になのかが歯痒くて、暗闇に迷い込んでしまったように涙が止まらなかった。
そうして13年。あの時なぜそう思ったかもわからないほど息子はよく笑い、よく笑わせてくれる。
何の特別もない。ごく普通の、これで当たり前の毎日なんだということに、なぜあの時は気付けなかったのだろう。
最近新しい出生前診断の話が報道されている。ダウン症などの染色体異常が胎児のうちに解るという医療技術の画期的進歩。しかし同時に安易な命の選択につながり兼ねないと倫理的カウンセリングの重要性も慎重に検討されている。
ダウン症は知的障害を伴う。
ようやく生まれた子どもに「障害があって良かった」と思う人はいないだろう。誰しも五体満足で元気に生まれて欲しいと願っている。
もしもそれが叶わないかもしれないと解った時、妊娠の継続自体を「どうしよう」と考え悩むのは当たり前かもしれない。
13年前の私が言う「そうだよ、だって怖いもの」
13年経った私が言う「そうだよね、でも楽しいよ」
プラタナスの坂道を上り、初めてお会いしたご夫婦も同じ。
「どうしていいかわからない」
そうだよ、誰だって知らない世界は怖いもの。
でも今、その時の話は笑い話になっている。
あんなに暗い顔をしていたのに「イヤ~言わないで~恥ずかしい!」って。
それからみんな口を揃えて言う「かわいくて、かわいくて」と。
知ってしまった世界は、思い悩んでいたよりもずっとチャーミングで笑いに充ちている。
またドクターから連絡があれば息子と共に「おめでとう」を告げに、この坂道を登って行くだろう。
命の質を問うてはならないと、このプラタナスの坂道を登る日が無くなることを願いながら。
一次選考通過 『しあわせ時間』 髙野 ひろみ
子供の忠告などには耳を仮さない、可愛げのない母だった。子供のすることには人一倍口うるさい、うざい母だった。御年77才。大人になっても親からみれば子供は子供と言いきり、親という鎧を外すことはなかった。
ある日バリバリ元気印の母が、ぜんまい仕掛けのねじの切れた人形のように動かない。はて、どうしたものか。救急車で運ばれた先で告げられたのは脳梗塞。いやいや先生、持病は心臓、なので脳であるわけがない。頭の回転は早いし、計算も早いし、可愛げないし、うざいし。心の中で意味不明なことを叫んではみたものの、病状に適した治療がすぐさま始まった。
神様、仏様。気軽にでる言葉に心底すがったことはない。なのに今回ばかりは意識せずとも脳裏を駆け廻る。可愛くなくてもいい、口うるさくてもいい、どうか神様仏様、助けてください、お願いします。
そうして数日後、気丈な母はいなくなった。正確にはその変りなのだろうか、すっかりアクの抜けたわらびのような気負いのない母とおもわれる人がそこにいた。入れ歯を外した顔など見せたことがない、それすら弱味とおもうのか、初めて見る顔に、あら、意外とかわいいんじゃない。
まもなく未知の生活が始まる。入れ歯を洗い、髪の毛を束ね、着替えを手伝う。ごはんの支度やトイレに付き添い、お風呂に入れる。考えもしなかった俗にいう親の面倒をみる、という行動が子育てをしていない私は日に日に面白くなってきた。アクの抜けた母は頗るかわいい、親バカならぬ子バカと言うのか介護が楽しくてしょうがない。手が動き、足が動き、無表情から笑顔になり、持ち前のがんばりもあって何年もかかったけれど、ひと通り自分のことができるようになってきた。欲もでてきた。食べたいものや見たいもの、聞きたいことやしたいこと。一生懸命生きてきたのだ。この先好きに過ごせば良い。
ところでアクの強い癖のある、あの性格はどこへ行ってしまったのか、先生が血栓と共に取ってくださったのか。
そういえば最近の私は、「ほれ、何してるの」「ほれ、言ってるでしょ」とほれほれおばさんになっている。こんな子だったかな、と首を傾げる母に、育てたように子は育つと可愛いげのないことを言い放っては煙たい顔をされている。それでも良い、こんなに楽しい時間と一緒に過ごせる環境を頂いた。
神様と仏様はひょっとして、母ではなく私を救ってくださったのか。それではもう少し願い事を、とはいくら何でも恐れ多い。
ならば亡き父よ、その日がくるまで見守っていてください。
一次選考通過 『パノラマ銀河に雨が降る』 P.N./伊良原ゆずる
上を向いても真っ暗だったので、僕は星空を見下ろした。
「星…見える?」
心配そうな唯の声。
「やっぱ展望台に来ても、雨じゃ星見えないや」
「そっかあ」
嘘の1つや2つ、つきたかったけど僕は正直に答えた。
今日は3000年に1度といわれる、流星がシャワーのように降り注ぐ日。二人で同じ時に、同じ星を見て、願いごとをしようと言い出したのは唯の方だった。
「こっちは、相変わらず星綺麗なんだけどな~。でも全然流星見えないよ。博の実家のシャワーの勢いでいいから星降らないかな?」
「悪かったな」
小さい頃から、家が近いこともあり、家族ぐるみで唯とはよく遊んでいた。誕生日やクリスマスはもちろん、暇があったらお互いの家を行き来してて、観察力のある唯の方が僕の家のことを知っているのかもしれない。
「ねぇ、もし流星見れたら何願うの?」
「そうだなぁ。人生楽に生きられるようにとか…」
「あ~あ。聞いて損した。ついでに願い事を人に言うと叶わないから、人生楽するのは諦めて他の願い事にしなね」
本当の願い事なんて、今ここで言えるわけないだろうと思いつつ聞き返した。
「言うと思う?」
「思わない」
「よくわかてるじゃん」
「まぁな」
1つ年下のくせに唯は僕に対しても生意気だ。
「電話代もあれだし、流星も見えないから電話切ろうか」
「なんだよ。俺は展望台に上ったりして、唯につきあってやったのに」
「電話してたら、せっかくの展望台も楽しめないしょ?」
「そういうことじゃなくて」
「受験生は忙しいの、じゃあね」
あっけなく電話は切られた。自分勝手なところのある唯だが、今日はやけに強引だ。怒らせたわけでもないんだけど。
目の前を見ると街は滲んでいた。パノラマ銀河に点いては消えるビルの明かり。それを縫うように家路を急ぐ無数のライト。
――唯に会いたい――
「わっ!」
懐かしい温もりが背中に衝突した。
「来ちゃった」
そこには黄色いワンピースに着せられた唯が照れくさそうに立っていた。
「なんでいるの?」
「会って第一声がそれ?」
「だって学校とか…受験生じゃん」
さっきまで、普通に話せてたのに、言葉がなかなか出てこない。
「一緒に3000年に一度の流星見たかったから」
顔がニヤけそうになった。
「と、でも言うと思った?息抜きというか、勢いというか、なんとなくだよ」
実家を離れてまだ4か月とは思えないほど唯の笑顔が懐かしく嬉しかった。
「雨、止みそうもないね」
「シャワーのように降ってるのが星じゃなく雨だもんな」
「でも、それでもいいんだ。久しぶりに博に会えたし、私は流星に願うより自分で夢を叶えるタイプだから」
「どういうこと?」
僕は唯が何を言いたいか何となくわかっていた。
「だから、今私がんばってるんだ」
僕は星空を見下ろし、唯の願いを応援した。
「来年待ってるぞ」
一次選考通過 『教わる』 P.N./愛田 光輝
四月中旬。この日、一通の封書が届いた。差出人は中沢絵里。それが誰であるかはすぐに分かった。懐かしい名前であった。
――玉山昌吾先生。ご退職おめでとうございます。先生、私を覚えていますか。小学校一、二年生の時お世話になった中沢絵里ですよ。母から「確か、玉山先生退職のはずよ」と教えられて、私も気がつきました。母が先生のお年を覚えていたのです。あれからもう三十二年が過ぎたのですね。
絵里の手紙には結婚して子どもが一人いることも書かれてあった。差出名と最初の数行だけが旧姓であった。
絵里が不登校傾向にあると知ったのは迂闊にも入学式を三週間も過ぎてからだった。
「絵里ちゃん、お母さんと一緒に来るよ」
と言う子どもの一言に驚いて家庭訪問をすると、一人では学校へ行けないということがわかったのだ。そういえば絵里は教室でいつもぽつんと一人だったし、友達が遊びに誘ってもいやいやをするだけだった。私といえば専ら子ども達が起こすトラブルの解決に意識が向かっていた。
私は不明を母親に詫びた。母親の話から推測すると、原因は人への不安であるように思えた。
私は母親と、絵里の学校での友達作りの見通しを話し合った。父親も時々対話に参加した。何度も家庭訪問をし、軌道修正をした。
やがて絵里は少しずつ誘ってくれる友達と遊ぶようになり、三学期に入ると友達と登下校をするようになった。
それなのに絵里が突然、一人で帰ると言い出したのだ。雪の降っている日だった。「心の中を聞かせて」と言っても首を横に振った。
私は放課後、絵里に一人ぼっちにならないでと説得した。屈んでいる私の肩の上に頬を乗せ、絵里はたくさんの涙を流した。
次の日の絵里の日記。
――わたしはなおちゃんたちがいっしょにかえろうといってもひとりでかえります。でも、あしたからいっしょにかえるよ先生。うまくいくかなあ。わたしはしんぱいです。
私は絵里の日記を読みながら少し安心した。
ところがそれから五日後の朝、絵里の右の眉毛の半分がなくなっていた。奇妙な顔だった。私は母親にすぐ電話をした。絵里が自分で毟り取ったというのだ。原因は五日前だ。そう私は直感した。絵里は一人になりたがっている。でも私には不安だった。
私は自宅の机に向かい、絵里との交換日記を何度も読み返した。蛍光灯の音だけがジージーと小さくなっていた。突然、一つの言葉が私の脳裏に躍り出て広がった。自由……。
絵里は、はじめて自分の意思で『一人で帰る』ことを選択したのではないか。それは絵里の行動の自由が広がったからこそできたことではなかったのか。それを逆に私は絵里を閉じこめようとしている。なんと浅はかな。私は指導という名の強制を恥じた。絵里にすまなかった。
次の朝、登校する絵里を玄関で迎えた。
「ごめんね、絵里ちゃん。先生が間違っていたよ。一人がいい時は一人で帰ってもいいよ」
頷く私の顔を見て、絵里は本当に嬉しそうに微笑んだ。
絵里はやはり一人ぼっちではなかった。その日によって選択していた。絵里は一人で歩き始めたのだ。
絵里の手紙には、母親から聞いた話もあるのだろう。「先生にはたくさんのことを教えていただきました」と書かれてあった。
だがそれは違うのだよ、絵里さん。先生こそたくさんのことを教えてもらったのだよ。そして少しずつ教師になっていけたのだよ。返事にはそう書こうと思った。
一次選考通過 『桜』 P.N./椎名 リサ
自分自身が敵になる事もある。頭の中をもどかしさや不安が占拠して思考がネガティブになる。相手が他人なら回避する術はあるが、それが自分となれば逃げられない。不安が駆け巡る内に、なぜか二十九年間の歴史の嫌な出来事までも思い返され、笑ってしまいそうになるのをグッと堪える。公園のベンチで一人で笑えば不審者確定だ。子供連れもいおれば、訳アリな人も来ていて、平日の昼間だというのに、賑わっている。「お姉ちゃん、どうしたの?」声がする方には、心配そうな顔の少女と少女の母親が立っていて、母親は私と同い年くらいで、自分のもう一つの人生と対面した様な気分だった。「えっ、あっ、何でもないです」我に返って答えたそのたどたどしさに母親が笑いながら話を続ける。「この子が“あのお姉ちゃん、ずっと下向いてる”って心配していたので声をかけました。驚かせて、すみません」――私、下向いてたんだ。――気づけば下を向いている事が多かった。そして、今日も……娘に遊具で遊んでくる様促すと隣へ腰掛け、たわいもない話を始めた。――あれ?あの子、小学一、二年くらいのはず。――だけど、理由を聞かれたくないのは、お互い様か。ふと「最近よく下向いちゃうんです。それでさっき……」ともらすと真剣な顔つきで耳を傾け、すっと立ち上がり「見せたい物があります。ついてきて下さい。」娘の元へ行き「桜、見に行こうか。」と声をかけた。嬉しそうに歩く親子の後ろをとぼとぼとついてゆく。――桜?もう咲いてないんじゃないかな?――十分程歩いた所で「ココです。」橋の下には川一面に桜の花びらが敷き詰められていた。「下を向かなきゃ見られない景色もあるんですよ。無理に前を見ようとしても眩しくて、よく見えません。きっと、この桜が咲いた時には、自然と前どころか上を向ける様になりますよ。その時に思う存分景色を眺めたらいんです」。母親が一人言の様に桜を見ながら、呟いた。「そうなれるかなぁ……」。私も一人言の様に呟く。すると、こちらを向いて「それが来年かもしれないし、もっと後かもしれない。でも桜が咲く頃を目標に少しずつ見方を変えていくんです。そしたら、この先に見える景色が楽しみになりますよ。その時に見る桜は綺麗にだろうなぁ。そうなりましょうよ。ねっ」「は、はいっ」。気迫に負けたのかは定かではないが、桜を見たいと思ったのは確かだった。そこからは、また、たわいもない話をして親子と別れた帰り道、ワザと下を向いて歩くと、くたびれたスニーカーが見えた。――新しい靴を買いに行こう。――いつもより軽い足どりで進むこの道の先が楽しい事ばかりではないのは、知っている。たとえ自分自身が敵だとしても、立ち止まらず歩いてゆこう。綺麗に咲いた桜を見るために。
一次選考通過 『自分占い』 P.N./和泉 えり
この街は、冬が長い。
鉛色の空模様ばかりで一面銀世界だった景色がようやく色付き始めて、緑が顔を出す前のこの季節が一番清々しいと僕は思う。
妻は、まだ枯れ木の茶色ばかりで何が楽しいの、と言うけれど。
外に出るたび、今日は暖かいとか、今日は肌寒いとか、少しづつ近づく春の気配に一喜一憂できるのも今の季節だけだ。
いつもの朝、通勤道路。
近文駅前から旭西橋まで一直線に伸びる道を、いつものように愛車に妻を乗せて走り抜ける。
左右に並ぶ建物から一枚の絵のように丁度中心に旭岳が見えたら、今日はラッキーデーだ。
「ちょっとは気分が上がった?」と妻が言う。
「ちょっと上がったかも」と僕は答える。
最近は会議ばかりが多くて朝が憂鬱なのは彼女も知っている。
少し離れた薄曇りの朝でも、こんなふうに真っ白な山が山頂までクッキリ見えれば、僕の中での『自分占い』は吉になるのだ。
実は空模様は、ほとんど関係ない。
例えば、家を出てから橋を越えるまで、ずっと信号が青なら小吉。
例えば、対向車に金運上昇の黄色い車があれば中吉。
そんな自分ルールな占いに妻は笑うけれど。
なんていったって、クライマックスは橋の中心、僕のテンションは最高潮に上がる。
「やった!」
朝陽に輝く石狩川の向こうに大雪山系が一切の雲掛かりもなくパノラマで広がっていれば、今日の僕は誰が何と言おうと大吉なんだ。
午前のプレゼンでとちっても、午後にお得意様に叱られたって、僕の気分は下がらない。
僕がそう決めた限り、僕の『自分占い』は絶対だ。
世の中はきっとこんなふうに考え方一つで全てをひっくり返せるんじゃないかと僕は思う。
それにはきっかけが必要だから、他人に笑われても物好きだと言われても気にしない。
だって偶然の景色だけで毎朝気分がちょっとだけでも上がるなら、文句なんかないじゃないか。
日々の仕事に疲れを感じていても、気の乗らない朝を迎えたとしても。
「この道がさ、ずっとずーっと真っ直ぐだったら、あの山の天辺に登れそうな気がしない?」
ラッキーな風景には、僕の空想だって広がる。
「私なら橋の50M上空に青い椅子を置いて、この街を上からゆっくり眺めたいなぁ」
空想話になら妻だってのってくる。
何故青い椅子なのかというと、こんな青空の中なら保護色になるから地上から気づかれないし、50Mなら道行く人の表情も見えるからだそうだ。ちょっと現実的な空想だけど。
こんな「大吉」な日は、お互いが現実に戻る頃には笑顔になれる。
そんな考え方でも、今日はラッキーデーになる。
自分勝手。
でも、楽しい。
明日は雨予報。さすがに澄み渡った山並みは望めそうにないけど。
僕と妻の『自分占い』は日々進化して毎日をラッキーデーに変えていくのだ。
一次選考通過 『秘密』 山崎 篤子
教会は、このプラタナスの並木を過ぎた先にあったはずだ。瑞希は三十年前の記憶を辿りながら歩を進めた。自分でも分からない衝動に駆られて病院を抜け出し、朝一番の汽車に飛び乗ってここまで来てしまったけれど、今頃夫は私の姿が見えないことを不審に思っているだろう。
遠くに雪を抱いた大雪の山並が、眩しく光っていた。五月の北海道の風はまだ冷たくて、急に不安を覚えた瑞希は足を速めた。
教会はあった。うっかりすると見逃してしまいそうなほど、慎ましやかにこじんまりと街中に佇んでいた。中はひんやりとして薄暗い。
朋子、あんたのお葬式以来だね。瑞希は囁いた。来なかったのか来られなかったのか、自分でもよく分からない。私雄三さんと結婚したのよ。貴女が結婚するはずだった雄三さんと。もし貴女がトムラウシで滑落したりしなければ、私はあなた達夫婦のいい友人で終わったわね。恋心をそっと隠したまま。
彼、今病気なの。一ヶ月持たないかもしれない。
朋子に初めて出会ったのは大学の入学式の時だった。何となく視線を感じて振り向いた先に彼女がいた。その年の夏休みには彼女の実家に遊びに行き、忘れられない一夏を過ごすことになった。初めての北海道旅行。登山が趣味の彼女に誘われて、山にも登った。きつくてあれだけは勘弁してほしかったけれど、そのお陰で雄三と知り合えたのだから文句は言えないと瑞希は思ってきた。山小屋で、三人共同じ大学だということが分って本当にびっくりしたものだ。
瑞希が朋子の魅力の虜になったように、彼もまた彼女に惹かれていくのが手にとるように分った。一足早く社会に出た雄三と婚約した年の晩秋、一人大雪からトムラウシの縦走に向かった朋子はそのまま帰らぬ人となった。
雄三が朋子の影をずっと引きずっていることは分っていた。子供が出来ていたら少しは違っていたかもしれないと瑞希は思う。
「死ぬのも悪くないな、彼女に会える」
昨夜、病室のベッドの上でぽつりと雄三が呟くのを聞いた瑞希は激しい衝撃を受けて、思わず口から出かけた言葉をかろうじて飲み込んだのだった。
(知らなかった?朋子が愛していたのは貴方じゃなくて私だったのよ)
あの時葬式から戻ると一通の手紙が瑞希を待っていた。一言、貴女を愛しているわと書かれた手紙。差出人の名前は無いがまぎれもなく朋子の筆跡だった。平凡で何の取り柄も無いと言う瑞希を、そこがいいのに自分では分からないのねえと朋子はよくそう言って笑ったが、手紙のことは誰にも打ち明けられないまま封印してきたのだった。
帰ろう。朋子が自殺を選ぶとは思えない。真相は永久に分からないのだもの、秘密は秘密としてこれまで通り自分の胸に収めておこう。
ゆっくりと教会の扉を開けると、薄暗い中からいきなり眩しい外の光に目が眩んでちょっとたじろいだ後、瑞希は力強く一歩を踏み出した。