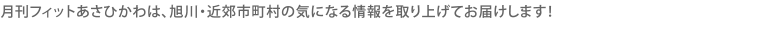admin
一次選考通過 『葉っぱのお面』 西 由佳
川が好きだ。湖よりも海よりも。
曇り空の下、鉄道橋の袂に腰を下ろし、留まるところを見つけられずに滔々と流れゆく水たちを、私は見送る。
今日は授業参観だったけれど、ママと一緒に帰る気にはなれなかった。美人で明るいママはクラスの母親の中でも断トツだ。――お父さん似なのね。今まで幾度となく投げ掛けられた言葉は、私の内に澱のようにどろりと溜まり、目の前の流れのように去ってはいかない。
ふと、視線を感じて顔を向けると、人が居た。大人だけれどとても小さな人。小さい頃ママが読んでくれた絵本に出てきたコロボックルによく似てる。
「おや、寄り道ですか」。傍らのランドセルに目をやったお爺さんの柔和な目。安全な人のようだ。少し離れて静かに腰を下ろした小さな人は、手ごろな葉を優雅に一枚拾い上げていじっている。よしよしという呟きと共に広げられた葉には穴が四つ。小さな顔にぴったりの大きさだ。
「素適なお面ですね」。あながち社交辞令というわけでもない。一瞬で素顔を覆い尽くす緑の能面に心惹かれたのだ。小さな人に倣い、自分の顔ほどの葉を見つけ穴をくり抜く。顔に当ててみると、目も鼻も口も寸分違わぬ位置にあった。
「上等なオモテが出来ましたね。溜まりで見て御覧なさい」。勧められるまま水溜まりを覗き込むと、誰だか分からない私が暗く映っている。面の下で笑ったり怒ったりしてみたが、水鏡に映る顔はどこまでも無表情だった。
夢中になっていたのか、列車が橋を通過する轟音で我に返ったが、顔から面を取ろうとした刹那、焦りと恐怖がせり上がってきた。剥がれない。葉の面が顔に張り付いて破ることすら出来ない。狭い視界で小さな人を探したがどこにも居ない。いつしか、サーッという音と共に雨が降り出し、私は立ち尽くした。
不意に、後方でガサガサッと鳴った。誰かが来る。音に背を向けたままがむしゃらに葉に手をかけたが、びくともしない。足音が近づき、鼓動が早鐘のように鳴り響く。見られる――。
「よう。何してんだ」。背中で聞き覚えのある声を聞いた途端、あれだけ張り付いていた葉がはらはらと落ちた。呆然とする私をよそに「水切りの特訓してたんだ。最高六回!」などと威張っている。お前は…と言いかけて私の足元から穴が四つ開いた葉っぱを拾い上げた。いつの間にか、手の平大の同じ様に穴が開いた葉っぱも持っている。「小人とお面ごっこでもしてたのか」。いつものからかいの口調に返答できず、顔がこわばる。
と、ヤツはおもむろにポケットから大きめの石を取り出し、私が緑の能面を映していた水溜りに叩きつけ、手にしていた二枚の葉も破り棄てた。「こんなものいらねえだろ、お前は」。視界が涙でぼやける。雨が降っていてよかったと思った。
一次選考通過 『氷解』 石河 周平
君が旭川高専を三年で修了し、メディア関係の専門学校に行きたいと言ったあの夏、私は賛成できなかった。
幾度となくあった父子のバトル、そして君が東京に向かう春の朝、黙々と荷物を詰めていた君に私の惜別の言葉が届いていただろうか。君は東京に出ると直ぐにバイトを始めていたのだね。仕送り通帳の残高が一向に減らないことが心配だった。君はそうやって君の決意を示していたのだね。お母さんとは連絡がとれていたことは知っていた。しかし、私との音信不通はあの朝から続いていた。
私はある賞を受賞するために久しぶりに東京に出てきた。幸便よろしく私は知ろうともしてこなかった奇妙な名称の学校や、そこでの君の様子を知りたくて、昼下がりに知らせなく向かった。月日が私を少し変えていた。
教員から、「息子さんは学生会館に帰っているでしょう。今日締め切りの作品があったので徹夜をされていたはずです。これが息子さんの課題作です。それは私の目からも君が才能を開花させつつあることを、そんな評価を教員がしていたことが嬉しかった。学校を辞してその後、胸の高ぶりを聞きながら、しかしどこかでまだ喉に魚の骨が引っかかったような思いで君の処に向かった。
君が東京に出てきて初めて訪れた学生会館、受付で君の部屋番号を聞かなければならないという父子の関係に、改めて複雑なる思いがあった。あの朝からもう一年半が過ぎていた。私はどんな言葉を君にかけたらよいのか分からなかった。
部屋の扉をノックするが応えがない。静かにノブを回すと赤子のようにベッドに突っ伏していた君の姿。バイトに疲れ課題をこなす日々だったのだろう。躊躇いながら、
「お父さんだよ、ほら、お父さんだよ」。なかなか目覚めない。そのまま寝かしておこうかと部屋を出ようとした時、寝ぼけ眼で君は、
「あれ?ここ何処?」
「旭川じゃないよ」それが、一年半ぶりの私の精一杯の言葉だった。君は私の思いがけない登場に、二人の間にあった時間を見失っていたようだった。
見るからに痩せた君に心が痛む。「さぁ、ごはんを食べに行くよ。まだだろう」。君は少しはにかみながら、「分かった、今着替えるから外に出て」
「何を今さら」
「いいから、外に出て」と、私の背中を押す。すると君は突然、背後から覆いかぶさるように私に抱きついた。
「嗚呼懐かしい。お父さんの臭いだ」。君がまだ小さかった頃、職場から帰るとこうやって足元に纏わりついたね。夕日が差し込む部屋に訪れた時の休拍(?)。
私は暫し君の体温を背中に感じながら、鼻の奥がつんとするのを、それを啜る音を覚られないよう斟酌しながら、改めて押されるままに廊下に出た。
私は私の頑固さを心から詫び、声を殺して一人泣いた。恥ずかしくも溢れる涙に、張っていた気持ちの糸がプツリ、と切れた。
あの夏以来、私の中にあった旭川の冬の氷柱のような尖った蟠りを、君の無邪気な唐突さと体温とで、一瞬にして氷解させてくれたのです。
一次選考通過 『父のカメラ』 高橋 正虎
あの写真は僕が撮った最初で最後の父の姿だった。
厳格だった父は僕の事を良く叱った。僕はそんな父が嫌いだった。
しかし、あの時は違った。
写真を撮る事が好きだった父は、どこへ行くのにもカメラを持って歩いていた。父の愛機は骨董品と言っても良いような代物だったが、それは大切に使っていた。
普段そのカメラは、書斎にある机の中にしまわれていた。だがその日はなぜか居間においてあった。
居間に入った時、何か不思議な感覚を覚えた僕の視線は、一度なりとも触らせてもらった事のない父のカメラに吸い寄せられていた。
気付くと父のカメラを手に取っていた。
ずしりと重く、ひんやりとした金属の塊から、どこか父を思わせる不思議な感触が手に伝わってきた。
いい気になった僕は、一丁前に父の真似をしてカメラを構えたり、ファインダー越しにいつもとは少し違う景色を見たりしていた。
父が居間に入ってきたのはその時だった。
「怒られる」
固まってしまった頭の中はその事でいっぱいになり、ただ茫然と立ち尽くすしかなかった。
だが意外な事に父の言葉は穏やかだった。
「なんだお前、それに興味があるのか」
父の問いにただ首を縦に振る事しか出来なかった。しかし、その声には優しさと嬉しさの感情が入り交じっていたような気がした。父はその返事に満足したのだろうか、「そうか」と一言呟いた後、隣に来て嬉しそうに言った。
「そいつの使い方を教えてやろう。どれ、貸してみなさい」
それからしばらくの間、父からフィルムの入れ方や設定の仕方、ピントの合わせ方やシャッターの切り方を優しく、丁寧に教わった。
その時の父の顔は、普段堅い顔をしている父からは想像出来ないような、とても、楽しそうな表情をしていた。
「よし、それじゃあ俺を撮ってくれ」
一通り使い方を教え終えた父は僕に向かって言った。
父は写真を撮られる事を嫌っていたんだったので、今日はどうしたのだろうと思いながら、僕はたった今教えてもらった手順でカメラを操作して、撮影の合図を掛けた。
ファインダーを通して父の喜色満面な顔を見ながら、シャッターを切った。
「カチリ」
小気味の良い音を立てて、カメラは父の姿をフィルムに写した。
「俺が死んだら、このカメラはお前の物だ。大事にしろよ」
今まで嬉々とした表情をしていた父は、ふと寂しそうな顔を浮かべた。
この時なぜ父がこんな事を言ったのか良く分からなかったが、僕の目にはそんな父の姿が印象的に写った。
その後父と散歩に出掛けた。二人でこんな風に歩いたのは多分初めてだったと思う。
日が暮れるまで歩いてフィルム一本分の写真を撮った。
帰りに近くの写真店にフィルムを現像に出した。一週間掛かるそうだった。
「お前が初めて撮った写真か。楽しみだ」
嬉しそうな父は写真が出来上がるのをとても楽しみにしていた。
しかし、父はその写真を見る事は出来なかった。
「約束だったからな。あのカメラはお前のだ」
父の最後の言葉は僕に向けてだった。
今、僕の首には父のカメラが掛かっている。
一次選考通過 『太郎の薬袋』 田辺 りら
どうしても誰かに読んで欲しくて、この原稿を書いている。
大学時代、鈴木太郎という友人が居た。記入例みたいな名前に似合わず、顔立ちはネパール人にそっくりで、人混みで目立つ程ひょろりと痩せて背が高かった。
太郎は二浪の末にやっと受かった札幌の大学で、たまたま私と同級生になった。出席番号の並びが近い男女十人で、富良野にラベンダーを見に行ったのを機に、同じメンバーでよく集まっては温泉に行ったり、びっくりドンキーで安いランチを食べた。
太郎は一人暮らしなのに8人乗りのボロボロのハイエースに乗っていたから、いつも車を出してくれた。スタンリーキューブリックが大好きで、床が見えない程に物が散乱した太郎の部屋で、キューブリック作品の分厚い本だけは、きちんと棚に収められていた。
去年の正月休み、家族と沖縄に旅行中の夜、私の携帯にメールが届いた。読み始めたとたん、島酒のほろ酔い気分が醒めた。同じグループだった沙耶からのメールは、太郎の死を告げていた。深夜だったが、私はすぐに沙耶に電話をかけた。
まだ四十代の私達は、訃報の衝撃を語り合った。
「太郎に普通に年賀状を出したら、お父さんからそんな知らせが来て吃驚したわ」。
と沙耶は沈んだ声で言った。死因は聞けずじまいだ、という沙耶の話は私を不安にした。
大学卒業後、太郎は故郷の関西に就職し、私は道北で公務員になった。もう15年は会っていないし、年賀状も出さなかったけど、太郎とはまた会えると思っていた。結婚しようが親になろうが、再会すれば学生気分で酒を飲めるはずだった。そんな友の訃報は悲しすぎて、考える度に涙が出た。
太郎の死の理由がどうしても気になって、私は旅行から戻ると彼の父親に電話をかけた。
「太郎くん、体調悪かったんですか?」
と尋ねる私に、父親は、
「仕事が決まらんで、ずいぶん悩んどって…」
と語尾を濁した。その口調から、私は自殺なのだろうと推察した。
太郎は最初に入った会社を辞めたらしい。それ以上聞けず、お悔やみを言って電話を切った後、猛烈な悔しさが襲ってきた。多分太郎が一番苦しんでいた時期に、私は何も知らなかった。通夜で思い出を語り合うことも出来なかった。だから、誰でもいいから話したくて仕方がない、太郎がどんなに不思議で、面白い奴だったかという事を。
香典を送った数日後、古い荷物を片づけていると、私の名前が書かれた薬袋が出てきた。中にはビニールの梱包材の切れ端と、手紙が入っていた。
「あなたは卒論でストレスがたまっています。これをプチプチしてすっきりしてください」。
太郎はそうやって冗談めかして気遣ってくれる奴だった。
このタイミングで出てきた思い出の品が、太郎からの香典返しに思えてまた涙が出た。
もし何十年後かに天国で太郎に会えたら、私は昔のままの痩せた猫背を思いっきり叩くに違いない。
なんで一人で先に行っちゃったのさ、と。
一次選考通過 『福寿草』 岩野 国広
芽吹き始めたプラタナス並木を運転して、私は週に五日この病院に来る。
貧しい農家の二男だった私は、中学校での成績は悪くなかったが、定時制高校に入学した。陽のある内は農作業を手伝い、一人で夕食を摂り、二キロほどの砂利道を通った。下校する中学の級友の姿を見ると、目を伏せて通り過ぎた。農作業の疲れから、睡魔に襲われることもしばしばだったが、休みの日も自宅学習は欠かさなかった。四年生のある日、「全日の生徒と一緒に、大学受験の模擬袰試験を受けてみないか」と担任から話があった。進学できる状況になかったので受けても仕方がないと思ったが、親友のA君とB君の勧めもあって受けてみることにした。結果は、三百人余りの中で三十八番だった。結果をみて、担任からも親友からも、進学するようにと強い後押しがあった。自動車関係の仕事をするのが夢だった私は、学費では迷惑をかけないから、と父に進学を懇願した。そして、室蘭にある工業大学に合格。奨学金を受けて勉強し、夕方からはアルバイトの毎日だった。それでも、下宿代を払い本を買うと、自由に使える金など無かった。
進学した年の七月、親友から連名で現金封筒が届いた。その中には一万円札が二枚入っていた。「俺たちは、先日ボーナスをもらったよ。これを学費の足しにしてくれないか」という手紙が添えられていた。頬を伝う涙を拭うのも忘れて、私はその手紙を何度も読み返した。夏冬のボーナス期の手紙と現金は、卒業するまで続いた。二人の励ましと送金がなかったら、異郷での四年間の勉学に、果たして私は耐えることができただろうか。
卒業後、苫小牧にある大手の自動車会社に就職し、エンジンの開発チームで力を尽くすことができた。
時は流れて、部長で退職した私は旭川に戻った。「月に一度は、三人か夫婦六人で呑もう」と決めて一年ほどが過ぎた三月、A君夫妻が大阪に転居することになった。長男が会社を起こすので、A君は顧問として力を貸すことにしたという。恩返しらしき事もできないままの旭川空港での別れに、周りの目もはばからずに肩を抱き合って泣いた。
そして、翌年の一月。B君夫妻が年始の挨拶に来てくれ、杯を重ねて思い出話をしている時、彼が激しい頭痛を訴えて倒れた。脳梗塞だった。一命を取り留めはしたが、右半身に後遺症が残り、今この病院に入院している。三か月ほどリハビリに歯を食いしばってきた彼が、杖の助けを借りてではあるが、今日は十歩余り歩いた。彼の萎えた手足をさすりながら励ます事が、私がB君に今できるたった一つの恩返しである。
雪に埋もれて耐えてきた福寿草が、プランターに植えられている。その花は、早春の陽光をいっぱいに受けて蜂蜜色に輝いている。それを自動ドアの向こうに見ながら、二人に返し切れない恩は社会に返したいと、案内係のボランティアとして、私は病院のロビーに今日も立っている。
一次選考通過 『過去』 袰地 哲
戸外に出、思わず立ち竦んだ。
そう、今、旭川駅から永山駅に到着し見慣れた昭和の匂いと汚れた色を残した乗降場と階段、改札口を通過した瞬間だった。
僕は、どこに来たのだろう?
昼の眩しい光線を浴びたピンクと灰色の高層建造物が空を遮るように二棟立ち並んでいた。
どこへ迷い込んだのだろう。微かな不安の中、しばらく佇んでしまっていた。
風景は一変していたのだ。僕はゆっくりと眼を移動し、景色と馴染むよう努力する。
正面に、くにさわ旅館の文字が朧げに眼光にそっと侵入して来た。高層住宅の影にひっそりと、それは見えた。あっと僕は呟き往昔の像が浮かび、ほっとした安心を取り戻した。
今も変わらない駅は小さく平屋で貧相なものだった。僕は昭和四十年頃、駅裏の長屋に住み、この道を国道のバス停まで通った。
駅前通りは。永山支所や瀬尾商店、生鮮市場と精香園、農協等客で賑わっていた。
あの時から何年経つのだろう?
数多くあった官舎や市場等も姿を消し、支所もグループホームに変じていた。
それらは、時の波に呑まれどこへ行ってしまったのだろう。僕は立ち止まり駅前道路を見つめた。一直線の先は、上川支庁を越え、遙か彼方に、霧の中から十勝連峰が見えた。
あの連山は老いや死を抱き生きているのだろうか。僕等は秒の時を刻み呼吸をしているのに。いや、あの山達は千年、億の世界を時をゆったりと駆けている。そう思うと僕はその姿に心を打ちのめされるし感動する。
駅前は、すっかり変貌したのだ。
広い歩道と空間、精錬された建物、すべてがコンパクトに調和が取れ、温かな景観となっていた。そこを歩むと思いがけない新鮮な感覚に包まれる。僕は前進し国道に向かう。
突然、様相が変わる。昭和のあの香りを染み込んだ建物が昔と変わらずそこにあった。樋口商店、永山医院、名画堂、前坂肉店等、昭和の染(しみ=ルビ)となって、浸透した空間だった。当時、樋口商店で筆を買った。
「高い筆よりこの安いのが書き易い」「儲けより客の喜び笑顔!」高笑いの社長の言葉。永山医院の年寄先生は通院時「飲み過ぎに注意!」と必ず最後に微笑んで言う言葉」
ただ、それだけの人と言葉の出会いだが、僕にとって人の喜びと酒への自制心は、今もなお生き続ける。
あの消えた街並にも、戦前の出兵の見送り、砲弾の音、悲鳴、そして戦後、食糧難を掻い潜って来た日々、悲しみ苦しみに耐えた人々の声が、ふっと浮かんで来る。
不思議な思いで、今、生きていることに、ほっと吐息が出た。
僕達は皆、過去で生まれ、時代の波に翻弄され育ち、形作られ、「今」と「秒」の世界に生き、「未来」を創る命の存在と思う。
皆、過去からやって来た人間なのだから。大きく息を吸い、また一歩進んだ。
一次選考通過 『小さな抵抗を母に…』 崎松 美恵子
先日私宛に一通の手紙が届いた。
茶封筒の裏にはある施設名と、幼い頃に私を祖父母に預け、そのまま行方を眩ました母の名前が書かれていた。
あまりに突然の事で気が動転してしまい。とても手紙の内容など読めず、上着のポケットにしまってしまった。
しばらくし、心を落ち着かせる為プラタナス並木の中へ散策に向かった。初夏の陽射しは今も私には正直あまり心地の良い感じではない。深い傷を隠しながら今まで生きてきた。私には一生忘れない心の悲しい記憶、それが甦っているせいかも知れない。
どのくらい歩いたのだろうか?池の側にあるベンチに腰を落ち着かせ、大きく大きく深呼吸をしてみた。
ポケットから手紙を取り出し、そっと目を向け読んでみた。
「突然のお手紙で、大変驚かれた事をお詫び申し上げます。貴方のお母様に関して大切なお話をしなくてはならず、一刻を急ぐ事ですのでお母様に変わり筆を取らせて頂きます事、ご理解下さい。お母様は現在重大な病に伏し、身寄りの無いとの事でしたので現在施設療養所にております。ご家族の方は貴方様ともう一人娘さんが居らっしゃる事でしたが、お母様と妹さんは、数年前より絶縁状態との事で、当方でも色々と手をつくしましたが、全く連絡も取れず最後に貴方様の元にたどり着きました。
お母様の病状は深刻で幾ばくも有りません。本人の願いとして、一目お会いして今までの全てを謝りお詫びしたく、最後のお願いとして和が娘達を探し出してほしいとの切実な願いを受けた次第です」。
今更随分自由に生きた母と会うなんて、と思いながら反面会ったら良いのか?と迷う自分がもう一人。後悔しないかと何度も何度も頭によぎりながら、どちらにしても後悔になる、会えば憎しみも沸いてくるだろう。反面、長い間出せなかった答えが見つかる気もする。平穏に何事も無かったと思う日々を願う自分も居る。
あれから幾日が過ぎたのだろうか?
母の終末を知った。
やっと心の中の荷がふと軽くなった。
結局私は母の想いを受け入れ、許す事すらも出来なかった。心の中は一切の悔いはない。
この世界に生を授けてもらった母に、最初で最後の抵抗を……。
一次選考通過 『故郷』 鈴木 雅子
私達親子が、旭川に越して来たのは二十年前。愛実が小学校入学を機に娘と二人、両手一杯の希望とほんの少しの不安を胸に、千葉を後にした。私の結婚は僅か一年半で破局してしまった。私二十五才、愛実はまだ生後十ヵ月だった。今に思えば、若気の至りだったかもしれない。なぜかその時、旭川に戻りたいと思った。それから七年、愛実の成長を待ち親の反対を押し切ってまでもこの町に拘った。
私は大学に通う為、プラタナスの並木道があるこの町で四年間暮らした。私にとって貴い青春時代だ。沢山の想い出と素晴らしい友人達と深い絆が出来た場所でもある。自転車に乗れる季節には、街路樹を渡りゆく風に吹かれながら通り抜け、歩道が落葉で埋め尽くされる季節には、靴の底から聞こえるカサカサと鳴る音を、心地よく感じながらゆっくりと散歩もした。春に成ると公園には桜が咲き誇り仲間達とお花見に出掛けたりもした。四季折々に街並みは表情を変えていく。そんなこの町が大好きに成った。卒業して千葉に戻ってからも、幾度となくこの町の景色、匂いを懐かしんだ事か。今はもう帰る故郷のない私達にとってこの町が、かけがえのない故郷となった。
愛実はこの地でのびのびと健やかに成長していった。小学校の時、子猫を愛しそうに抱えて帰って来た事があった。聞くと、並木道をよたよたと歩いていたと。そして家族の一員と成った。中学生の頃は、親には決して見せない微笑みを、仕事帰りの車中から見た事が有った。自転車を押しながら並木道を歩いている愛実。隣には素適なボーイフレンドが。きっとあれが愛実の初恋だったのだろう。高校の部活帰りに、教会から出てきた花嫁さんを見たと言って、目をキラキラさせて帰って来た事もあった。そして「ママ、私をこの町に連れて来てくれて有難う」そう言った。
それまで心の奥底でいつも自問自答していた。親の勝手で父親を奪い、忘れられない町だったと言うだけで、雪深いこの地に幼子を連れて来た事。越して来て一、二年は気候の違いに、身体が馴染めず辛い思いもさせてしまった。
本当にこれで良かったのかと、熱の下がらない愛実を見つめながら何度思った事だろう。でも、その答えを愛実が出してくれた。娘もまた、沢山の想い出と素適な人達との出会いがあったに違いない。
遠くへ嫁ぐ日が間近い愛実に伝えたい。元気で二人仲睦まじく幸せに暮らしてほしい。そして貴女には、いつでも暖かく包み込んでくれる故郷があると言う事。明日への力を蓄えるべく翼を休める場所、そこを人は故郷と呼ぶのでしょう。いつの日か「ここがママを育ててくれた町よ」と言いながらプラタナスの並木道を、娘家族が歩いている。そんな事を思い浮かべるだけで、口元は緩み目元は緩んだ。
荷造りを手伝う手が、ふっと止まっては二十年が走馬燈の様に駆け巡った。
一次選考通過 『母』 佐々木 虎力
母が病で倒れたのは戦後間もない昭和二十一年の春、雪解けが遅い三月の終わりの頃と記憶している。留萌沿岸の鰊の漁場で飯炊きの仕事があるからと言って出掛けた母。
その時、旭川の国鉄管理局から深川の国鉄保線区単身赴任をしていた父は勿論のこと、家族全員が猛反対したが、母は笑いながら言った。
「辛くなったらすぐ帰ってくるから心配しなくていいってば…」
家族に心配を掛けたくない母の心遣いなのであろう。しかし、それは貧しい家庭の台所を必死になって守ろうとする母の並々ならぬ決意の表れだと受け止めた。
数日後、母が飯場で病に倒れたことを国鉄の電話で知らされたとき、父は意味不明な言葉で怒鳴ったように記憶している。
その夜、父は最終列車で母を迎えに行った。母が寝ている布団を担架ごと貨車に運び終えた父は懸命に母を看病した。しかも、やん衆や女子衆の迅速な対応で、無事に帰ることができた。早速、旭川市立病院に緊急入院。診断の結果、病名は骨盤カリエスという難病であった。現在であれば一本二十数万円もする高価な薬を、一週間ごとに注射すれば治りが早いという医師の言葉に、父は何も言わずに従った。
両親は十人の子供を育てるため必死になって働いた。特に、母は体を酷使することもやむを得なかったのであろう。鷹栖の農家への出稼ぎ、日本通運会社の貨物列車からの荷下ろし、旭川駅構内の除雪など苛酷な労働に従事した。しかし、過労が原因で病気になったことを知った時、家族の嘆きと悲しみは計り知れないものもあり、途方に暮れた。
ただ、いくら辛くとも自己犠牲という感情に惑わされる事なく、ひたすらに慈しみの愛を家族にそそぐ母の姿に、深い絆と愛情を肌で感じた。だから疲れきって帰ってきた母に遠慮することなく、思う存分甘えることができたし、そのことがなによりも嬉しかった。
戦後の食料事情は困窮を極めていた。旭川の住民も、その日の食料を調達するため朝早くから買い出しに出かけるが、ほとんど手ぶらで帰ることも決して珍しくはなかった。わが家も同様であり、食事の時など止むを得ず芋粕・カボチャ・大根の葉など、食べられるものはすべてごっちゃ煮しながら食いつないだ。
夕食時、母が自分の食べ物を丼に盛ると、ちゃぶ台の上に置き、子供たちが食べ終えるのをじっと待つのである。末っ子の私が食べ終えると母は言った。
「虎力、母さんの食べていいのだよ」
その時、すかさず姉が言う。
「母さん!食べないと病気になるよ」
と母を気遣う。私が食事を終えると台所に行って腹一杯水を飲む。戻り際、さりげなく鍋の底を覗き、残っているときだけお代わり
をした。
戦後は確かに、ひもじい思いがしたが、兄弟姉妹が互いに助け合うこと、さらには、母が子供たちにそそぐ慈しみの愛こそが、豊かな人間性を育む糧になることを学んだ。
春の彼岸になると、何時も思い出すのが母の姿。合掌する気持を忘れない。
一次選考通過 『八年目の春』 佐久間 尚子
三月というのに、朝、カーテンを開けるとブリザード状の雪が荒れ狂っている。「あ、今日もか…」。いささかうんざりした顔で、じいちゃんとばばはソファに腰を下した。毎日毎日除雪にあけくれる。朝食後、お互い薬を飲み、小降りになるのを待ち武装して外に出る。玄関フードには雪がべったりとはりつき、階段は深く深くうづもれている。よたよたしながらママさんダンプをおしている姿はみていてさぞかし滑稽だろう。じいちゃんと、ばばの力は二人で一人前?いや半人前かもしれない。ようやく終わって部屋にはいると、すぐ按摩器のとりあいになる。二人とも腰が痛くて痛くて我慢できない。旭川は地震も台風も少なく本当に住みよい町であるが大雪だけは年とともにこたえる。そんな時、娘から検査結果、異常なし!のメールがはいった。
「本当?おめでとうー」。すぐ返信した。うれしくて、うれしくて今までの疲れや腰の痛みがどこかへふっとんでしまった。じいちゃんと、ばばは手をとりあって喜んだ。
思いおこせば二人の孫が小学四年生と三年生の時、娘が発病した。頭が真っ白になり、何も考えられなくなったその時、三年生の女の子が「お母さんでなく、ばばがなればよかったのに」。なにげなく言った。ぎょっとした。
「そうだね、ばばは年をとっているし、お母さんはこれからあなた達を育てていかなければならないから、ばばがなったほうがよかったね」。ようやく答えたような気がする。孫は悪気はなく、心の底からそう思ったのだろう。
孫達は高校生になり、勉強(?)と部活動に励んでいる。「昔、ばばにこう言ったんだよ。おぼえている?」。聞くと「そんな薄情なこといったかな?」とケロリとしていた。
娘も元気で夫婦プラス、じいちゃん、ばばで孫の野球応援に夢中である。昨年は全道大会にも出場でき円山球場まで出かけた。ハラハラ、ドキドキしながら目一杯パワーをもらい、めちゃめちゃ楽しませてもらった。
今年は最後である。ばばの二番目の願いは孫が毎回試合にでられることと、ヒットを一本でも多く打ちチームに貢献し、よい想い出づくりができればこんなうれしいことはない。じいちゃんはそんなにうまくはいかないというが、先日、練習試合で初ホームランを打ったと娘からメールがきた。うれしくて天にも昇る気持ちだった。早速、夜「初ホームランおめでとう」のメールをしたが、返信は「ありがとう」のひとことだった。北国のおそい春とともに娘夫婦、じいちゃんとばばの応援行脚がはじまる。
なんといっても一番の願いは娘が元気で九年目、十年目、これからずっと永久に春をむかえることである。
それが叶うなら、じいちゃんもばばも大雪ぐらい我慢しよう。